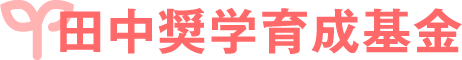田中奨学育成基金について
公益財団法人田中奨学育成基金は、青少年育成に尽くした故田中正行氏の精神を受け継ぐ遺族の意志で、昭和47年に郷里の長崎で『財団法人田中正行奨学育成基金』として創立されました。
「学業ができるものが進学できず、できないものが金の力で進学できる。そんな世の中では教育の機会均等にはならない。才能は個人のものではない。世の中に尽くしてこそ人間としての意義がある。」と財団発足の基調を当時の理事長田中功氏は語りました。
財団の設立規模は(拠出金、相続評価額が約1億円)、基本総額4800余万円。初年度の予算概略は400万円の経常予算で、奨学生一人当たり年額9万6千円。20名を予定していました(実際には創立年度採用者数は18名)。その後奨学金を利用する学生は順当に増え続け、昭和52年には累計90名を超えました。
貸与資格は、学資に困る学生が対象でした。大学は全国どの大学でもよく、特に医学生には貸与期間を6年に延ばして便宜を図ったことも特長の一つでした。
一方では創立から2年後の昭和49年に、社名を『財団法人田中奨学育成基金』に改称し、そして平成24年4月より公益法人として、新しく生まれ変わりました。
創立から52年、令和4年までに350余名の学生が私共の奨学金を利用しています。
これからも微力ではありますが、青少年教育助勢の一翼を担うべく事業を継続してまいります。
① 法人の目的(定款第3条)
この法人(公益財団法人田中奨学育成基金)は、長崎県内地域における教育、文化等の振興を図るため、必要な助成を行い、もって社会の発展に寄与することを目的とする。
② 事業内容(定款第4条)
この法人は、前条(定款第3条)の目的を達成するために次の各号に掲げる事業を行う。
⑴ 学校教育法第一条に規定する学校のうち、大学に在学する長崎県出身者に対する奨学金の貸与
⑵ 青少年の教育、文化活動の奨励
⑶ その他目的を達成するために必要な事業
③ 沿革
| 昭和46年 | 「財団法人田中正行奨学育成基金」設立発起人会開催 |
| 昭和47年 | 創立(理事長 田中功氏)、事務局を「長崎市大黒町」に構える |
| 昭和48年 | 長崎県に「試験研究法人等」に係る証明を受ける(以降隔年で昭和62年まで実施) |
| 昭和49年 | 「財団法人田中奨学育成基金」に社名変更 |
| 昭和55年 | 長崎市社会教育課図書整備室に図書寄贈(以降平成元年まで毎年実施) |
| 昭和58年 | 田中憲子氏理事長就任 |
| 平成元年 | 長崎県に「特定公益増進法人」申請、認定・証明を受ける(以降隔年で実施) |
| 平成2年 | 市立図書センターに図書寄贈(以降平成19年まで毎年実施) |
| 平成3年 | 長崎地域留学生交流推進会議(現長崎大学外国人留学生後援会)へ寄附(以降毎年実施) |
| 平成4年 | 創立20周年記念式典開催 |
| 平成5年 | ㈳ガールスカウトに本連盟長崎県支部へ寄附(以降毎年実施) |
| 平成6年 | 長崎少年合唱団育成会(現長崎少年少女合唱団)へ寄附(以降毎年実施) |
| 平成13年 | 事務局を長崎市賑町に移転 |
| 平成20年 | 田中理事長、長崎市より市政功労賞を受賞 市立図書センター閉館に伴い、市立図書館に図書寄贈(以降毎年実施) |
| 平成24年 | 公益認定を受ける。公益財団法人田中奨学育成基金に移行 |
| 平成27年 | 事務局を長崎市賑町より長崎市浜町に移す |
| 令和4年 | 創立50周年 |
| 令和5年 | 田中廣氏代表理事就任 |
| 令和6年 | 長崎市より長年の図書寄贈に対し、感謝状を授与される |
④ 設立根拠法
民法第34条(法人の能力)
第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
⑤ 主務官庁
長崎県教育庁
⑥ 事務局の住所
長崎県長崎市浜町8番3号 株式会社タナチョーホールディングス内
電話番号 095-822-4576
年次報告書
令和7年度 公益財団法人田中奨学育成基金役員
評議員(7名)
丸山 真純
湯口 隆司
松永 安市
初村 一郎
林 亜紀子
西田 潤
寺平 安伸
理事(6名)
田中 廣
山﨑 賢一
田川 耕太郎
河内 和人
西 経一
中富 武満
監事(1名)
富永 泰弘